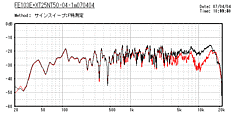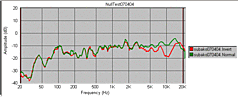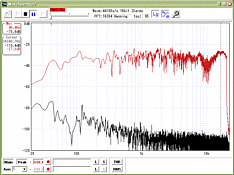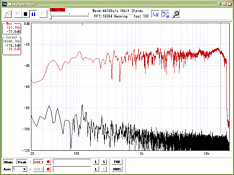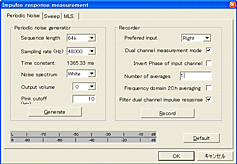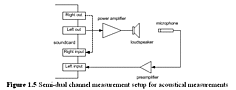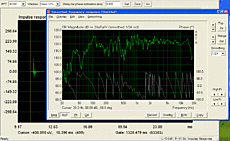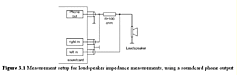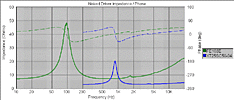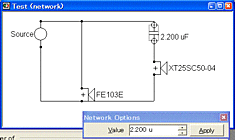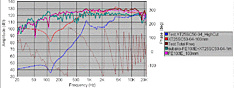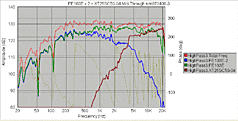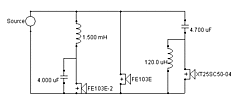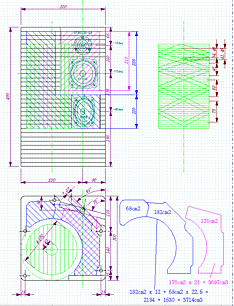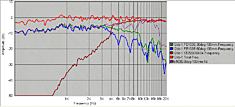オヤさんが ARTA必要十分マニュアルを公開してくださいました。
有難く、使わせていただきます。(^^)/
早速、MLS信号でインパルス応答を周波数解析する手法でF特と群遅延特性を測定してみました。 (インピーダンスは測定は明日の予定)
まずは周波数(SPLと位相)から。
こんなに低音、出てたっけ?
少し低域が持ち上がった結果に見えます。
ゲートを設けず、FFT時間で計算しているから?
ちなみに、マイク補正はオヤさんのところの(修正版)を使わせてもらってます。
MySpeakerだとこんな感じ。
聴感上はこちらが合っている気がする・・
ARTAの使い方が悪いのかなあ・・
一応、群遅延特性も表示させてみました。
スパイラル共振のすぐ下の35Hz付近で山があって・・ていうのは納得ですが、もっと遅れが大きそうなものだけど、、 それに、?150Hz付近は割りと平坦だし。 やっぱりきちんと測定できていないのかな。
中域の暴れはすごいなー。 これは部屋の影響だけではなく、スパイラルからの音の遅れも大いに影響している部分だと思います。
(以下後日、インピーダンス測定の結果も貼り付ける予定)
追記:測定時間を延ばしてFFT数を上げると、低域の測定分解能が上がってレベルも下がってきます。そして群遅延は低域でもぎざぎざに。
追記:右図のように、時間軸でみたレスポンスに、インパルスの立ち上がりが出ないのは、変。 サウンドカードの入出力の非同期とかが原因かなあ・・
オヤさんのところで少し騒ぎになってますもので、私も少し測定してみました。
WaveSpectraというソフトで、オーディオなどでサインスイープ波をリアルタイムで高速フーリエ解析し、ピークホールドして測定グラフとする、という手法です。
この手法の信頼性の低さの指摘に対して、「信頼性が低いのはご尤もだけれども、どれくらいダメなのか」が良くわからない。
オヤさんのところで公開されているデータが全てであれば、「こりゃ、全然だめじゃんか」ってなことになるのですが、 私のところではさて、どうなりますことやら。
比較対象としては、国内標準とも言えるMySpeakerと、海外では定番(?)のSpeakerWorkshopです。
まず、測定時の構成から。 テスト中のため仮止めです。
MidRange:(Fostex)FE103E
Tweeter:(Vifa)XT25SC50-04
Network:2.2μFのハイパス1本のみ (^^;;
なお、測定レベルはソフトによって、まちまちです。 1W(2.83V)は入っていないと思いますが、0.1W以上は十分に入っている状態での測定です。
また、マイクはECM8000で距離1mですが各ソフトで補正は統一していません。
【測定結果】
まずはお手軽にMySpeakerのサインスイープから。(以下MS)
いい加減なハイパスだけなんで、フルレンジ状態のMidの高域と干渉してうねってますし、このネットワークでは深い谷にはならないですね。
ツイーター接続を反転させた場合(赤)は明らかにレベルが落ちて、10KHzの谷が深くなってます。
続いてSpeakerWorkshop。(以下SW)
ゲート測定ではなく、通常の測定です。 1/6 Octaveでスムージングをかけているので、急峻な谷は均されてますが、ほとんど同様の結果です。
最後に、問題のWaveSpectra(以下WS)
ソースシグナルは上記SWで作成、200ポイント+スムーズ、リニアスタイル、スイープ時間180sec。
WSのFFT数=16K、窓関数=ハニング、fps数=80?100
左がノーマル、右が反転。 縦軸のスケールが違うので他の測定結果よりも小さめに見えますが、埋まるような感じでは無いですね。
**
以下、考察および私見です。
今回、私は10Khz付近でのリバース接続でWS+sinスイープでも、そこそこの測定結果を得られることが確認できました。 本当は、オヤさんと同じくらいの500Hzあたりでテストできれば良いのですが、その環境がありませんのでお許しを。
また、今回の結果をもってオヤさんのデータを否定するものでもありません。
結局のところ、もし「WS+sinスイープ」による測定法が「信頼性の低い方法」だとしても、使用者がそれを認識しながら使えば良いのだと思います。
もちろん、他の方法を使えれば良いのですが、何より「音楽を聴きながらリアルタイムで音圧スペクトルを確認」したり、その流れでsinスイープでピークホールドされる様子を高調波歪のレベルも見ながら測定できる、 という直感的なわかりやすさが得られるからです。
この方法を使い続けることは私も推奨しませんが、 最初から「この方法はだめだから使うべきではない」 とは言いません。
初めて測定する人には、こういった方法から入ることで、知識と聴感・直感でやってきたことを目に見える形にすることの面白さ、すばらしさが十分に伝わるからです。 ステップアップはその後に行えばよろしいではないですか。 時間は十分にあります。
「この道は、いつか自分が通ってきた道」
まずはお詫びです。 昨日のARTAの測定ははっきり言って「失敗」です。 「触ってみた」だけと思ってください。 (ならBLOGにアップすんなって。ごめんなさい)
でも、昨日の不調の原因が判明しました。結構落とし穴かも。必見です。
そして、ユニットインピーダンスの測定も行い、各ユニットのNerFieldのSPL・Phaseデータと共にSpeakerWorkshop(以下SpWs)にインポートして、現状のハイパスフィルターのみのネットワークシミュレーションを、「練習してみました」
【1:昨日の不調の原因】
ARTAはDEMOバージョンで動かしていると、設定値を保存できません。 不覚にも、「Single Channel」 での測定になっていました。
右図「Impulse Response Setting」 の「Dual channel measurement mode」 にチェックを入れないと、ダメだったのです。
また、マニュアルによると、私の測定環境は Lchをsoundデバイスからループバックする「Semi-Dual Channnel」 測定 というものに該当し、 右図のようになっています。(但し、L/Rは逆です。 SpWsにあわせたので・・)
おそらく、サウンドカードの種類などの環境によっては、ループバックを必要としない「Single Channel」 測定がうまくゆかない場合があるのだと思います。 私の場合も(USBサウンドカードだったりするし??)、そのクチだったでしょう。
改善の 結果、右図のようにインパルス立ち上がりから測定でき、MySpeakerと同様のSPL結果を得られました。 ヤッタネ。(^^)/
【2:Limpでインピーダンス測定】
ARTAに同梱されている「Limp」:
[Program for Loudspeaker Impedance Measurement]
を使って、ユニットの裸のインピーダンスを測定し、SWにインポートしました。
まず、測定には高出力アンプは不要です。 サウンドカードの「Phone」出力があればこれを使えます。 アンプ出力の減衰回路が不要ですし、初心者には安心です。 接続は右図のようになっています。 (今度はL/Rは図のとおりにしました。)
☆ただし、オヤさんによると この方法はFsに少々誤差が出るようです。まあいいか。。☆
測定には、2モードから選択可能で、私の環境では以下のような違いが出ました。
(1)「PinkPN」 (周期的ピンクノイズ)
100回測定して自動的に平均を求めてくれる方法ですが、外乱の影響を受けやすいのか、グラフのFsの山が綺麗にでませんが、こちらを使いました。
(2)「Stepped Sine」
単一周波数のsin波を短時間測定して、周波数をインクリメントしてゆく方法。 高域で荒れたので、使いませんでした。
(まあ、Fsの山が少し乱れてもさして影響はなさそうなんで、(1)「PinkPN」を選択してマス)
測定が終わったら、メニューの「File」?「Export ASCII As」?「Plain ZMA File」を選び、ファイルに保存します。 この後は、オヤさんの ARTA必要十分マニュアルに書かれたのと同様の方法で、SpWsにインポートすることが可能です。 (右図は、別のチャートに重ね合わせたもの)
以下、SpWs(SpeakerWorkshop)の説明です。
周波数応答もインポートしたら、各「Driver」の「Driver properties」の「Data」タブで、インポートしたインピーダンスと周波数特性を関連付けます。
その後は、オヤさんのSpeakerWorkshopチュートリアルの 5. クロスオーバーネットワークの設計 を見れば、シミュレーションが可能になります。 テストした現状ネットワークはハイパスだけの詰まらないもの(右図)。
そうして行った結果のグラフが、右です。
なお、FE103Eは裸だと2KHzに大きなピークが現れたので、subakoにマウント状態で測定。 ツイ?ターも4KHzにピークがありますので、これも後日バッフルに付けて測定しなおします。
***
今回の「練習」により、今後の測定・シミュレーションのスタンダードとなりうる感触を十分に得ることができました。 SpWsのチュートリアル/ARTAのマニュアルを公開していただき、オヤさん、本当にありがとうございます。
*** 追記070409
この手の軽量コーンのフルレンジほど、コイルを通した時の劣化感があります。 折角、生きの良いフルレンジをMidに使うのですから、ここだけは何とかしてスルーで使いたい。 そういう思いでいろいろいじってました。 で、割とまともな特性が。
ネットワーク図。
かなり変則的です。
位相の干渉を見ながらのシミュレーションが必須ですので、この手の方法でないとほとんど無理ですね。 慣れると面白いです。
アイデアだけは溜まってきました、コンテスト向けスピーカー。
先週末、subakoを使ってARTA+SpWsで占ってみたものの、テスト用に使用したコイルが 0.7mH - 0.4Ω と抵抗値が大きく、 ダンピングが悪化して折角のスパイラルの音の躍動感が無くなりボンついた低音になってしまいました。
悩んだ挙句、一時期あった「あっち向いてホイ」方式を実践することに。。
元々、ネットワークを通すことには消極的だったのですが、 EF103Eをハイカットしてツイーターに引き継いだ場合の音の透明感、奥行き間の向上が忘れられず、なんとかしてフルレンジのままでツイーターと融合できないか、と考えていました。
しかし、FEスルーでツイーターを7KHz程度で12db/Octで繋いでみても、FEの高域とーツイータの合唱は耳障りになるばかりで、逆効果とも言える状態。
# ボンツキのない躍動感や鮮度を取るか、音の透明感・見通しを取るか・・
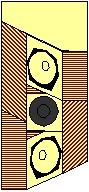
|
そんなとき、先人の知恵を思い出しました。 フルレンジなんて「あっち向いてホイ」 すれば指向性の高い高域はかなり減衰され ツイーターともそのまま繋がりそうです。
予想される特徴は以下。
- 正面か ら見るとバーティカルツインで、定位感バッチリ。 リスニングポジションを多少左右に移動しても、FE103Eの高域のバランスも変わるのでセンター定位 は大きくブレない。 但し、上下方向には多少振れる、席を立ったり座ったりすると、FE103E同士の干渉で5?10KHzのレベルが落ち込みそう。
- フルレンジ側はネットワークスルーなので、何より低域のダンピング悪化もなく、中域のフレッシュさも減退しない。 ついでにネットワークパーツ代を節約できる。
- 内部の3D?スパイラルは2条巻きで、なおかつ上下に入口と出口がクロスする方式に初挑戦。 こうすることで、ダクト出口を上面と下面にしてこれもバーティカルツインとなり、中低域の定位向上と内部容積の有効活用が図れる。
- 上記と引き換えに、当初予定の直径序変スパイラルは不可能となった。 位相を序変することで、ホーン形状とする予定。
- 内部構造は複雑の極み。 けれども元々積層構造で大変なので、設計時間はかかるが製作時間はそれほど大きく増えない(と思う)。
- バッフル板の交換構造は採用できない、たぶん。。
名前は「Twister」、 別名 「ヒネったの?」 です。
今回は、楽しんでできそうな予感がします。
本日は忙しくなかったので仕事は休み。 (^^;;
Twisterの設計図を仕上げました。
↑ 33枚の積層合板、1枚たりとも同じ物は無いのですが、 円筒スパイラルのディスク部分と箱の枠部分を別に書くことで、図面枚数を減らしました。
今後、これを原寸大のテンプレートに書き出して、板取りを行います。
作るのも、大変そうです。 (T_T)
連休中にはとてもじゃないけど完成しません。 できるだけ楽しんでやろうと思います。
ちなみに使う工具は一般的なものばかりです。
- 電動ドリル
- 電動ジグソー
- 電動ディスクグラインダー
- その他、一般的なハンドツール
- 果てしない気力と、尋常でない体力
なお、M8-L480mmボルトは市販品はありませんので、溶接ボルトを特注としています。
#設計が終わって少しほっとしていますが、本番はこれから?。
#さてと、見積もり仕事を片付けなきゃ。。
***070427追記
問題発生。 シナベニヤの厚みが、15.5mm/1枚 ありまして。 33枚重ねると、511.5mmと規格オーバーです。(笑)
ツイーター付近の1枚を抜いて、スパイラルを1段下げる設計変更で対処します。 これで32枚で、496mm! ふう・・
本日、会社の決算業務を妻に伝授して、その作業の完了を待つ間に設計してみました。
(070420画像を入れ替え)
ハッチングの意味は、、
ピンク色がFE103E-15degの空気室
水色がFE103E-45degの空気室
若草色が2条巻スパイラル(設計中、2条を各空気室で専用に分離し、共振周波数や中域ピークの分散を図ります。)
第一ダクト共振=35Hz
第二ダクト共振=42Hz
となります。
空気室容積をかせぐため、こんな形になってしまいました。 だいぶ無理がある設計だなあ。。 こんな形は積層スピーカーでないともっと大変ですね。(笑) これで容積的には何とか入ることがわかりました。
FE103E-45degの空気室の下には、予定どおりIMMB(音響インピーダンスマッチングボックス。。?) を付けられそうです。
Twister、 現在 subakoをあっち向いてホイ! して実験中。
現状subakoにFE103Eスルー x 1本 (30degオフセット) + ツイーターでテストしている限り、 かなり良い音を奏でます。 音場の見通しや弦の繊細さ、躍動感、音域バランスなど、FE88ES-R1発のsubakoを軽く凌駕します。
ただ、FE103Eを内向きにすると音像・音場感が損なわれるようです。よって、ツイーターを少し内向きとし、FEは2個とも外向きに変更。
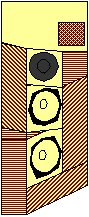
|
構想はこんな感じです。
正面を基準とすれば、
ツイーターは-15deg、
FE103E-1は+15deg、
FE103E-2は+45deg、 です。
ツイーターを基準にすると、
FE103E-1は+30deg、
FE103E-2は+60deg、 です。
ARTAで距離100mmで測定し、simuった結果は↓のようになります。 10KHz以上はツイーターの能率が少々低めですが、外向きFE103Eの高域のエネルギー増分があるので、ツイーター正面でのバランスはこのくらいが良さそうです。
また、5?10KHz付近が干渉でうねってます。
こ れは、フルレンジ側にネットワークが入っていないため、位相回転具合がツイーターと異なることから生じており、 この方法(フルレンジスルー)を採用する からには、致し方ありませぬ。 うねりの大きさが小さいので、元々のFE103E-0degよりも十分にフラットですね。
そろそろ設計製図に着手できるレベルに到達したように思います。
そして当初の見込みよりも相当に音の良いスピーカーにできそうです。 楽しみになってきましたよ?!
GWに突入しました。
今年は前半と後半に分かれていますが、前半は体力週間、後半はちょこちょことお出かけモードになります。
【前半の予定】
1、Twisterスピーカー工作開始
2、苗運び手伝い
3、テニスの練習
まずは設計が終了しているTwisterスピーカーの工作を開始。
材料は、15mm厚のシナベニア、600mmx300mmのカット品ですので、今回のサイズにベルトマッチ。 L/Rの積層部品を1枚ずつ板取りできます。
設計図から原寸大の型紙を起こして、1枚ずつケガキを入れておきます。 これは夜にもできる準備作業。
そしていよいよ本日朝から、気力と体力勝負のくりぬき作業。 まずは半分に切断してから、12mm木工用ドリルで1枚あたり20箇所くらいの穴をあけて、そこを基点にして各くりぬき穴をジグソーで抜いてゆきます。
今日は15枚xL/R分をくりぬきました。 単にくりぬくと言っても、構造が複雑ですんで、半端じゃなく大変です。 30分/1枚xL/Rたっぷりかか ります。 写真の左のほうにあるのが、くりぬいた端材の山です。 積層スピーカーの会管理人の面目躍如(?) (^^;;
とにかく、「一気に片付けよう」と思うと続きません。 マイペースで、リズミカルに呼吸をして有酸素運動でじっくりやらないと、だめですね。 (笑)
そして、途中でちょっとした設計ミスや作業ミスに気づきましたけど、細かいことを気にせずに続けました、これも一つのコツかも。
この続きは、5月1日にやる予定。 完成度、現在20%。
当社は2月末決算でして、 つまり2ヵ月後の4月末が法定調書提出の締切日なのであります。
昨年は4月に長期出張が入ったため3月に済ませましたが、 今年は余裕があってここまでずれ込んでしまいました(笑)。
月末はGWで休みに突入するということで、慌てて帳簿の記載を始めています。 今年はやたらと接待費が多いな。。 まあその時に自分も食べているわけですからまあ、おK。
毎年のことながら、この作業は面倒です。 でも避けては通れません。 明朗会計にしておかないと、税務調査の時にもっと大変なことになるんで。(汗)
これ、今年から 当社のもう一人の役員兼、WEB事業部長であります 奥様に一部を伝授しようと思っていますが、時間に余裕がないし、どうなることやら・・
ようやく、弊社のH18年度決算および確定申告が終了しました。 写真は昨年と同じになるので掲載しませんが。。
まずは本年度単期では黒字になりました。 昨年の損失とほぼ相殺。 良くできました、パチパチ。 でも役員報酬は思いのほか高くないんで、まだまだこれからです。
実は、確定申告に添付する法定調書の複写紙に書き込んでいる途中で、昨年の損失金額の誤りに気づきまして・・ (^^;;; すぐに税務署に電話で問い合わせて、修正後の損失額で記載することでOKとのお返事。 ヤレヤレ。
何はともあれ、これでH19年度の業務と趣味に(?) 集中できまする。
以下は、いつものリンクです。


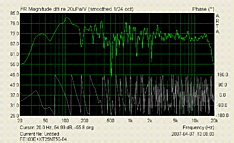
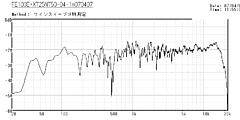
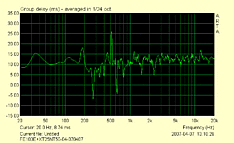
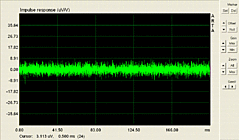
 3
3