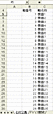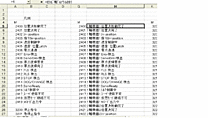今年のOMTOMO MOOKの付録は、なんと今や人気急上昇中のMarkAudio製、アルミマグネシウム合金コーンの8cmフルレンジユニット「OM-MF5」! 実は私自身はMarkAudioのユニットを使ったことが無いのですが、巷では大歓迎の様子で期待大です。発売直後の状況を見て、良さそうだとのことで買いました。
フレームが同社の市販ユニットとは違いプレスフレームで、少し板厚が薄めかな? しかしビス5本止め、十分な強度とリヤ開口面積。 制振処理をすればなかなか良さそうな感じです。
自作プリアンプのRchの音が出なくなっていたのですが、やる気を出して基板の裏からさぐってゆくと、ハンダ溶け込み不良2か所を発見し、修正完了。
そしてOM-MF5を、クリアミントにネジ1本で仮付けし音質の確認。2016年のFostexのアルミコーンや、昨年のPioneerのユニットに感じたような高域のクセが少なく、低域もよく出て全域で品位の高い音質と感じます。
ボーカルはFostexに慣れてしまった私の耳には少々大人しめですが、MarkAudioのフルレンジユニットはコーン絞りが浅めなので、そのためか音の広がりに無理がない気がします。
さすがに、FE88-Solと比べると情報量の違いで叶いませんが、中域を中心とした音のまとまり、まとめ易さでは勝っているかもしれません。付録ユニット史上最高音質かもしれませんね。 大好きな松岡直也などのフュージョン系を聞くなら、FE88-SolよりこのOM-MF5のほうが向いています。
コンテストも開催されます。締め切りが12月なので余裕がある反面、参加者全員の完成度が上がって、激戦になること必至ですね。
私も参戦する気持ちが高まってきました。 肝心のアイデアは少しづつ出てきていますが、まだ決定打に欠けます。もう少し、じっくり考えてから設計に着手しよう。
今作ろうとしている subako-extension スパイラルを積層で作ると、subako上部だけでなく本体の一部が積層構造となります。
そんな折、以前よりあった「積層スピーカーの会」を作ろう、という声が一部で上がりましたので、そろそろ頑張ってみようと思います。 もちろんスパイラルだけではなく、どんなスピーカーでも積層構造を使っていれば対象となるサイトの予定です。
まずは取り急ぎ、ドメイン「sekisou.org」 を確保しました。 現在取得手続き中で、もうすぐ使えるようになります。
続いてコンテンツです。 会社のサーバーを借用して構築する予定ですが、まず必要になるのは画像掲載掲示板でしょうか。 それと、情報共有として「PukiWiki」が便利かと思いますので、使ってみようかと考えています。
準備が完了したら、そこかしこで告知します。
ちなみに、
http://www.sekisou.com/
は「積層金型」の会社のサイトです。 考え方がそっくり・・
新年最初の作図となりました、3D-subakoの下部extension計画。 subakoの空気室部分を描いた時以来のCAD図です。(^^;;
右が平面図、左が側断面図。 ピンク色の上部本体からそのまま拡大円筒スパイラルに導き、本体後ろ部分で下面開口とします。
t18mmラワン合板を13枚積層で切削。 最下部3枚はビス止めにでもして開けられるようにしておこうかと思っています。
★ φ260mmのスパイラルは、国内最大級の記録更新?
12月23日の記事では伝統的な平面スパイラルに繋ごうかと思ったのですが、やはり円筒スパイラルの広範囲低域輻射特性を生かさねばと考え直して、この形になりました。
材料は11日頃に入荷予定なのでそれまでに全部品図を作図し、その週末に作業ができれば、というところです。 狙いは、32Hzまでの更なる低歪再生と量感アップ。 さてどうなるか。
***070103追記
部品図です。いずれも板厚18mm、板幅は300mmで、全幅が印刷範囲に入っていません。 黒ハッチングはくりぬき、紫ハッチングは傾斜研削。 (表と裏の両側のハッチングが同じ表記になっていて、区別を省略しています。)
部品1 部品2 部品3
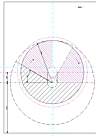
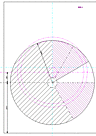
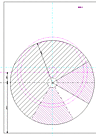
部品4 部品5 部品6
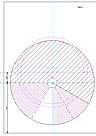
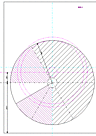
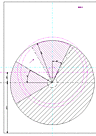
部品7 部品8 部品9
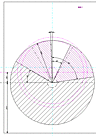
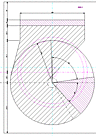
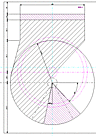
部品10 部品11 ;部品12
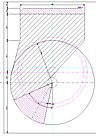
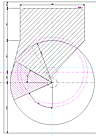
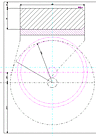
部品13
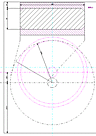
先日の報告で「秘密の拡散財」が3D-subakoスピーカーの空気室に入っていると書きました。 本日はそれを公開します。
こんなん
ダンプラの表面に、シリコーンシーラントをメレンゲ上に不規則な凹凸をつけて盛り上げたモノ。 これを園芸用ブチル両面テープで空気室内面に貼り付けてます。
私の環境では、ピアノの右手のアタックによる空気室内定在波の抑制にかなり効果がありました。 これと下部ディフューザーのお陰で、吸音材ゼロにできたわけでして。
興味のある方は、数百円で試せますので、どうぞ。 ダンプラを曲げれば、おそらく塩ビ管にも入ります。 ・・ もちろん、効果がなくっても恨みっこナシですよ。
本年1月に、携帯用テンプレートの件もあって公開勉強会に参加させていただいた時以来、ホダ塾メンバーに入れていただいておりました。
その間、HD1.0.3のリリースに際しては、携帯用テンプレートのコミットと、携帯表示の確認テスト・報告程度しか活動できておりません。
このような状況ですし、このたび訳あってHD開発者メンバーから退会することに致しました。...
東京ディズニーランドへ行ってきました。 朝7時過ぎに家を出て、夜8時過ぎに帰宅。
今週末より、クリスマスバージョンに衣替えしてのオープン。 ハロウインバージョンが終了しても、昨日の天候が悪かったためか気温の低さにもかかわらず普通に混雑していた。 
本日、Linuxサーバーのメンテ中に、下記コマンドでDisk-Raid(Raid-1:ミラーリング)から1台ディスクが解列されていることを発見。
# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid1 hda3[0]
154231936 blocks [2/ ] [U_]
unused devices: <none>
Tipsその2です。
32軸分のラダーのデバイスコメント。 皆さんどうやって書いてますか?
「1軸位置決め始動完了」 とか 「機器1位置決め始動完了」 などでしょうか。 これらだと、軸番号と機器名称の両方が書かれていないため、デバグの際にいちいち確認が必要になっちゃいますね。
こういう時こそ、MS-EXCELなどの表計算ソフトの出番です。
上のMS-EXCELファイルです。
![]() comment.xls
comment.xls
これで、「1軸機器1位置決め始動完了」 などとすることができます。 一度作っておけば、次回以降は「機器名称」部分32箇所を書き換えるだけでできちゃいます。
これを応用してあらゆるコメントを汎用化し、コメント編集を確実にスピーディーに行うことができ、 ひいては間違いのないコメントに基づく間違いの少ないソフト作成と立ち上げに結びつけることができると考えます。






 8
8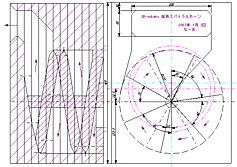





 でもまたそのうち、行きましょう。
でもまたそのうち、行きましょう。