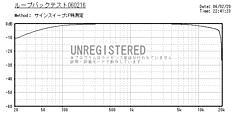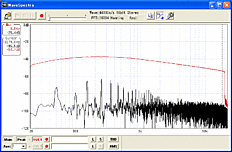日記一覧
当サイトに登録されている日記一覧


ようやく、subakoHS (人格変更版3D-subakoの新name)のディフューザー改良に着手しました。 10月6日の記事でテストしてきたものでして、口ばし状の隔壁 (あるいはホーンと呼ぶべきか) を取り付けています。
なお、スピーカースタンドも製作しました。 (11/19:右の写真を追加しました。グラインダーで仕上げ中の状態です。)
subakoHS (HighSpeed) のほうは、こうすることで中域の干渉が減ることと、低域の明瞭度が上がって低いほうに少し伸びたように感じます。 中域の干渉に自分の耳が慣れてしまったというのもありますが、十分に満足できる範囲に入ったと思います。
また、今まで置き台にされていたSuperSwan改を久しぶりに再セッティングして聞き比べてみたところ、低域はsubakoHSのほうが遥かに質が良 く、量感では劣るものの長時間の聞き疲れがしません。 スピード感のあるドラムスと相まって、JAZZ、FUSION系での得点は上がったと思います。
デザインに関しては、元のコンテストバージョンでは下部ディフューザーが90度回転させた位置で設計したため、余計な穴や溝などが開いたまま。。 塞ぐべきだとは思うのですが、手間が・・
スピーカー台については、30mm厚のシナランバーを切断後、接着の前にコバ面にシナロールテープを貼りました。 いやあこれは綺麗に塗装仕上げ したくなる出来です。 重量が軽いので音質への寄与という面ではあまり貢献していないと思いますが、それでも足の組み方を工夫したため、subakoHS 開口部の直下に空気溜りを作ることができ、低域の空振り防止に一役立っていると思います。 ユニット軸芯までの高さは、床面から875mmと低めになっ ています。
また、上方は天板を設けず、オフ会などでの運搬時には写真のように逆さまに重ね合わせて運搬スペースを節約することが可能としました。
以上、 11月23日の集まれ塩ビスピーカーのオフ会までは、多少仕上げが進む程度で参加することになります。 プレゼンの選曲も固まってきましたし、楽しみです。 参加の皆さん、よろしくです。
オヤさんのブログからトラックバックが飛んできたので、早速おじゃましてみました。
自作スピーカーの特性を、 Speaker Workshopという(私からみれば十分にプロ向け)ソフトを使って測定してらっしゃる。 ん、ナチュラルダクト的にバスレフポートにダンプラを入れての測定も。(残念ながら所望の効果は得られなかった様子であったが。)
普段せいぜいMyspeakerやWaveSpectraをおもちゃ機材に繋いでお気楽な測定しかしてこなかった私も、そのうち踏み込むべきところと考えていましたので、オヤさんのブログで少々勉強。 うん、コンデンサマイクとファンタム電源は知ってるし。 ん?ループテスト? おお成る程。 これ ならMyspeakerでも簡易にできそう、ってことで試してみました。 (オヤさんのブログでは RMAAというソフトで評価していました。RMAAでもやってみましたが、MyspeakerでのF特測定法と同様の結果でした。)
1、PC内: Myspeaker→ヘッドホン出力端子
→マイク入力端子→Myspeakerで測定。
なんじゃこりゃ。 高域・低域ともだら下がり。
高域はフルレンジには重要性低いとして、低域は予想をはるかに下回る悪さ。
2、思い直して、いつものテストCDをCDプレーヤでかけて音源とした。
CDP→AMPヘッドホン出力→PCマイク入力端子→WaveSpectraで測定。
はらほれへらふれ・・ メタメタです。 こんなんで測定していたなんて、笑ってください。わっはっは。 インピーダンスが合わないのか? なんて考える気にもなりません。
やっぱり、コンデンサマイクとファンタム電源だけでなく、サウンドインタフェースも買わねばならんのね。 フルレンジユニット1set分が軽く飛ぶ出費。 でもまあ、今後も継続してゆく趣味にこの程度の出費は仕方ないか。
タグ ESXi 自鯖

Tornadefly+ND25FA-4のネットワーク調整に入っています。
マイク(ECM8000)紛失し、Technicsマイクカプセルのアッセンブリもまだなので、耳だけを頼りに調整しています。
以前の単純な6db/Oct構成では、1uFでもフルレンジP1000の10KHz付近とのかぶりが耳についていたので、 0.05mH程度のコイルを自作して試してみました。
まだ微調整は必要ですが、P1000の高域を妙に強調することも無く、さりげなく高域の拡張がなされている感じになってきました。
もう一息、がんばって調整します。
今日は走法の話題です。
先日の企業対抗駅伝2018 東京大会 の練習にて、SSC (Stretch Shortning Cycle:伸張-短縮サイクル) のコツが少しわかってきました。
みやすのんき氏の「誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本」には、SSCで効率よく走るフォームの基本が、60のコツとともに書かれています。
- 誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本単行本(ソフトカバー) – 2017/12/27
内容をここに書くわけにはいきませんが、私が特に参考になったのは、1、「脛の速い前傾」 と、 2、モデルになって美しいフォームで走ってくださったサイラス・ジョイ さんの言葉「足の力は使わない。お尻と背中の力で走ります。」という部分。
1、については、サブ3.5程度のスピードですと、地面と体の相対速度も小さいのでなかなか実感しにくいのですが、駅伝の5km用のスピード練習でだいぶわかってきました。
最近ではあえて接地時に膝を一瞬保持して荷重を遅らせることで、脛が素早く前傾し、直後に重心真下に入り込んだ足に荷重を集中させることができ、結果として重心の少し前方に足を置いてもブレーキをかけることなく、スムーズにSSCで走れるようになりました。
私がアップしたものではありませんが、以下の動画も参考になります。
参考:キプチョゲ選手によるフルマラソン2時間の壁挑戦動画
2、については、以前もお尻と背中の力に注意して走ったことがありますが、その時は支持脚が重心を過ぎてから蹴っていました。 これは完全な間違いで、加速局面以外では疲れるだけです。
今回、上記1、との合わせ技で、荷重の際にリラックスして、お尻に意識を集中し、少し押し込まれる(股関節が曲がる方向)感じを意識しつつ、これを利用してバウンドするように走ると、お尻の筋肉もSSCを使った走りになることがわかりました。 太ももの筋肉の負担も減るように思います。
この1、と2、の合わせ技が上手に融合したときには、自分が弾力性のあるボールになったような、翼が生えたような、なんとも気持ちの良い走りができてきた気がします。
これでスピード練習も、長距離練習も鍛え上げて、フルサブ3.5に挑戦です!
年末から計画していた、不平衡/平衡ラインプリアンプ。 この3連休を利用して、パーツ買い出し、実装設計、製作、バラックでの音出しまで駆け足で漕ぎつけました。
- 買い出し
初日は買い出しから。 ケース以外は大体2台分のパーツ購入で、2万円オーバーの買い物になってしまいました。 抵抗はKOAの1/2W金属皮膜抵抗、ボリウムはマルツのR1610G-10Kを擬似Lパッド接続で使用。コンデンサは、日本ケミコン。 高価なオーディオグレードは使わずに始めてみます。
- 実装図
回路図はぺるけさんのを継ぎ接ぎで行けると思うので、タカスのユニバーサル基板 IC-301-72 への実装図から始めています。この基盤は、予め使いやすいパターンになっているので、どう配置しようか考えるだけでも楽しいですね。 以下の図は、音出しまでの修正済みのものです。
- 組付け
組付け順としては、まずは上面に配置するジャンパ線から。
コンデンサの大きさを全く考慮しないでレイアウトを決めてしまったので、抵抗の上にコンデンサが覆いかぶさるという不格好な姿に。
- 回路チェック
テスターしか持っていないので、チェックといっても電圧くらいしか見れません。 DC24VのACアダプタをつないだところ、FETが異様な高温に・・ 設計から再確認したところ、2SK246は脚の1番と3番が2SK117と逆順だということを失念していました。
そのほか、いくつか間違いがあったものの、無事に電源がまともに入るようになり、思い切ってパワーアンプに接続。無事に音がでました。
- 音出し最初の音質
ぺるけ氏のサイトには、アルミ電解コンデンサの酸化皮膜の自己修復が進みまでは音が落ち着かない、20~30時間は経ってから評価してほしい、とあります。
それでも始めから低域~高域までどこも特出したところが無い聴きやすい音でした。 鳴らしているうちに少しづつ、細かい音が出てきたように思いますが、今のところは解像度などまだまだというところです。
- 今後の予定
買ってきたケースに入れることと、細部のチューニング、オーディオグレードパーツへの交換など、地道に進んで行こうと思います。
- アッテネータへの交換(追記20180113)
製作後に100時間以上のエージングを終えたプリアンプを試しています。
うーん、どうにも霞がかった音でして、これはどうにかならないかと思案して、ごとうさん式アッテネーター(テスト版)の登場! 写真のようにバラックのままですが。。
これはすごいです。 ベールが2枚ほど取り去られたように、音像、音場、厚み、高域の細やかさ、全てにおいて自分史上最高音質が聴けています。MarantzのPM14SA-ver2に戻ることはもうあり得ませんね。
ここまでくれば、現在テスト版のアッテネーターをきちんと完成版としてコンパクトに作り直して、プリアンプのコンデンサをオーディオグレードに交換して、箱に入れます!
いやー、最高!!
コイズミ無線ネットで買い物していたら、なにやら気になる一文が。。
イベント紹介 > STEREO 8月号付録 FOSTEX製8cmユニット試聴会
おおーっと! 今年も付録が。 それもFostexから8cmメタルコーン。 これは5月21日(土) 13:00~15:00の視聴会に行かなきゃ 
他のサイト等ではまだ告知を目にしていないので、この視聴会の連絡が初告知でしょうか。
気になるコンテストがあるのかどうなのかは、今の段階では情報が少ないですが、何となくありそうですね。 





 2
2