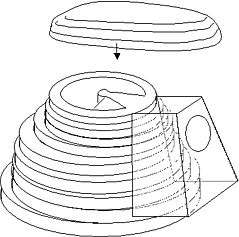日記一覧
当サイトに登録されている日記一覧


タグ ランニング シューズ 健康 Tarther Zeal
つい先日まで我慢しようと思っていた勝負シューズの購入。。ガマンできずに今シーズン3足目を購入しました。
先代の Tarther Zeal 4 Wide、ハーフマラソン、フルマラソンとも、ここぞという時に履いてきたお供でして、ほぼレース用として使ってきたので、ソールの減りも少なく、まだ十分に履けます。
でも、、ネットで見ると Tarther Zeal 5は新しいミッドソール「FlightFoam」が軽くてへたりもないため、従来よりも厚めに使っている、つまり軽いのにクッション性も向上している、ということのようでして。6が出たので型落ち品となり、Amazonで8,300円で購入できました。
今までのトレーニングの成果をこのシューズとなら心中できるという気になってしまったわけです。
恒例として、重量測定。 Wide 26cm 159g。4のWideが163gでしたから、2.5%の軽量化ですね。
あとは、当日のコンディション作りと、中盤まで上げすぎずに我慢することですね。 グロスでサブ3.5は厳しいので、ネットで狙います。
タグ 自鯖
(ナイキ)ズームフライ3を購入しました。
日常の練習用、および履き心地が良ければフルマラソンのレースでも使えるかも?という目論見です。
恒例の体重測定
- ズームフライ3:242g/26cm
- ズームフライ:219g/26cm
- ズームフライSPファスト:198g/26cm
やっぱりズームフライ3は26cmサイズで242gと重めですね。ミズノのウェーブシャドウの239gに近い。 初代ズームフライの219gより23gもメタボになったとは。。
実際に10Kg走ってみました。 いつものようにゆっくり入って、途中から徐々にビルドアップしてみたのですが。。 ゆっくりでも速くても重さのためか脚が前に出てこず、シザースタイミングが今一つ合いません。そのため、Neo逆ローリング走法の遊脚の慣性を上手に利用する以前に、慣性力が乗ってこない感じです。 もう少し走り込んで慣れれば少しは良くなってくるでしょうか?
ズームフライSPファストの198gは優秀ですね。 反発もあるしクッションもそこそこ、ハーフ迄なら現時点で所有するシューズ中のイチオシです。もちろんフルにも良いのですが、もう少しクッションも欲しいので、ズームフライ3との中間のものが欲しい。。 ズームフライフライニットが欲しかった・・
2月13日、メルカリでお古のズームフライフライニットを買いました。26cmで216gと、初代と同じくらいですので期待できます。

2016年初レース、第36回館山若潮マラソンを走ってきました。人生5回目のフルマラソンです。
昨年は大学後輩のS水くんの応援のために応援団で頑張っていましたが、次回はぜひ走りたいと思っていた大会です。
地元色が強く温かい雰囲気に包まれ、コースは30キロ付近の坂が特にキツイですが、それを乗り越えるとあとは平地で、大きな声援が待っていました。
応援団の方々にも、11Kmと33Km地点で力を沢山いただき、無事に完走できました。ありがとうございます!
タイムは4時間8分15秒、ネット4時間5分44秒でした。35キロからヘロヘロ、ペースダウンしましたが。自分的には4時間10分切れたので満足です。
| 計測ポイント | スプリット | ラップ |
|---|---|---|
| Start | 00:02:31 | |
| 中間 | 02:01:17 | 1:58:46 |
| Finish | 04:08:15 | 2:06:58 |
種目別順位 547/1224
総合順位 2256/5782
2014年stereo誌コンテスト応募作品「クリアミント」のスパイラル部の口径アップによりL/D比を小さくし、低域輻射域を拡大した改造を行い、「クリアミント2」としました。
完成後の音質は、元々よかった中高域にスパイラルの本来の低域の厚みが乗って、バランスがよく聴きやすい音になりました。
実質シングルバスレフなので低い方はサイズから想像するほど伸びていませんが、低域の厚みが出たことで全体のバランスも良くなり、フォアプレイのフュージョンが気持ちいいです。
ただし、この非力なユニットにスパイラルの位相30°/枚、ダクト面積30cm2は少し大きすぎるようで、低域のスピード感がなくゆったりした音質です。
もう少し位相を捻って、36°/枚、24cm2程度にしたほうがよさそうです。
今週末、 あだたら高原スキー場にLAFESTA(FF+スタッドレス)で行ってきました。
子供たちは初スキーでいろいろ大変な面もありましたが、家族の絆を深めつつ楽しい旅行になりました。 親バカの長文でよろしければ、どうぞ。
実は事情があって、金曜日に学校を休んで行ってきました。 2月10?12日の3連休で行く予定が、直前に長男が足に軽い怪我をして松葉杖を使う状態で行 けなくなり、止む無く延期したための日程です。 (こういうのは、学校はズル休みとは言いませんよねぇ。計画休とでも言いますか。)
【1日目】
金曜日の朝3時過ぎに自宅を出発。 神栖?大洗を抜け、水戸で国道6号線を経由して、日立南太田で常磐道。 そのまま磐越?郡 山JCTで東北道へ。 二本木ICで降りて(高速代は3,750円)、朝7時頃にはあだたら高原スキー場に到着。 いえいえ、多少は飛ばしましたがこんな に早く着くとは・・
(ちなみに帰宅時の給油で、旅程576Km/給油41.2L=14.0Km/Lでした。 2+2名乗車+荷物満載の条件では満足です。)
今週末のあだたら高原、金曜日は昼から雨、土曜日は快晴でした。前日の雨により斜面はガリガリのアイスバーン。その分人も少なく、初心者コースでもリフト待ちは1?3分。 それでもローカルスキー場なので食堂は普通に混雑。
最初は、このようにソリで遊んで、 →
午前10時?1時間半は子供はスキースクールに。 本当に初めてだったので、スキーの履き方から。
その間、「今しかない」とばかりに、有志の方からいただいた1日券2枚で、妻と私はリフトを6本。 初級コース?中級コースを滑って10年ぶりの足慣らし。 いやいや、ママも結構できるじゃん。
まずはハの字で止まることから。
しかし、こんなへっぴり腰ではどうにもなりまへんなあ。。
ここで雨が降ってきましたが、食事の後は少し上がったので練習を継続。 リフトを使わず、えっちらおっちら板を持って斜面を登るのは大変。 皆がんばりますた。。
その後雨がひどくなってきたので15時半に引き上げて、 岳温泉のホテル安達屋で温泉?夕食。 ふぐ刺とお酒までサービスでついて、美味しかったです。
【2日目】
快晴! 前日の雨で練習斜面はガリガリのアイスバーン。 少し練習したところで長男(小4)が「こんな凍っているところじゃあ滑れないよ!」などと我侭を言いだし、妻と休憩モードに。
その間に、次男(小1)は先陣を切って私とペアリフト初挑戦。 もちろん、アプローチ?テイクオフとタッチダウンは服をつかみあげて「お人形」状態でした(笑)
何とか上に上がって、だましだまし「大きなハノ字!」の努力空しく10回以上転びつつ、それでも私に似て頑張り屋さんの次男は、「また転んじまった?。むずかし?。でも次は大丈夫!」などと独り言をいいながら、降りれました。
さて、お汁粉でご機嫌を直した長男、また少し練習した後、4人でリフトで登りましたが、期待を裏切らずタッチダウンで見事にコケてくれました。 すぐに横に避けられたので止めるまでは至りませんでしたが。(笑) その後も何度かコケましたが、リフトは一度も止めず。 5回目くらいで最初からハ の字で降りるように教えたら、安定して降りれるようになりました。 教える方も勉強ですね。
初級コースリフトで上って撮影したもの。
山頂だともっと絶景だったんだろうなあ。
何とか4人で降りて、次男は力尽きてお休みモード。
その後は長男メインで、妻と私が交互に初級者リフトで上って降りて。 初めはハの字でも↑のヘッピリ腰ですからエッジが効かずにほとんど「直滑降」に近かったのですが、終わりの頃はしっかり左右に曲がったり止まったりできるように。。 子供の学習能力には恐れ入ります。
加えて夕方、私が2本ほど一人で中級コースを楽しみましたが、 その後を追って、少々だらしなかった長男が、一人で練習斜面をエッチラ登って頑張って練習してました。 いつも口ばっかりだと思っていた長男ですが、少し見直しました。
こうして楽しい想い出とともに、スキーを上手になるよう「みんなで頑張る」 という家族の絆を深めることができた、貴重な旅行が終わったのでした。 それにしても、家族スキーって親は想像以上に大変!
おっといけない、帰路で途中に「 原子力科学館」に寄ってきました。なかなか勉強になりました。
*** 補足
FFのLAFESTA+スタッドレスでしたが、道中はまったく雪がありませんでした。 スキー場へのアプローチでは急な勾配・ヘアピンカーブもありましたので、凍っていたらチェーン装着が必要な感じですね。
現行メインSPに鎮座した3D-subakoですが、浜辺の生録の音などを聞くと、ある周波数で微妙に(気柱共鳴とは違いますが)共鳴していま す。 一般には3D-スパイラルホーンから漏れてくる音は中高域がきれいだと言われていますが、これはあくまでCWホーンと比べた場合であって、円筒を音 道に使っていることから(その内径が一定であること故に)内径を2分の1波長とする周波数が基底の共鳴は必ず付きまとうはずです。200mmであれば、 860Hz付近。 3D-スパイラルホーンをお使いの方は、一度吸音材を取り出して浜辺の音を再生してみてください。 すぐに判ります。 (ト○レの排水 管を流れる水音みたいな、いやーな音です。)(T_T)
え、? 吸音材を使えば済む事? 確かに吸音材でだいぶ減ると思いますが、そうすることで中音以下の音の鮮度は下がる一方です。 3D-subakoでようやく吸音材無しでも聴けるレベルの物になったので、些細なことでも克服してもっと音の鮮度を上げたいわけです。
さてこれを回避するには、なーんだ答えは簡単。 内径を徐変させれば良いのです。 ・・と言うのは簡単ですが、作るのは大変、大変。
例えば、ご本家Takenakaさんのページに、 「ディスク法」という作り方が紹介されています。 仕切り付きのドーナツ型円盤を多数、位相を回転させながら積層してゆく方法ですが、 これで円の径を変化させればできちゃいます。 きっと、私以外の誰か既に思いついていると思います。
その他には、塩ビ管のサイズを途中で変える方法もありますが、接合部のスパイラル仕切りをどう作るかという別の問題が・・
ということで、やはり積層方式。
3D-yadokari案です。「やどかり」君に見えますよね?
あまり枚数は増やすと大変ですし、1枚あたりの厚みが厚いと、そのぶん仕切り板部分の斜め研削量が多くなって加工も面倒になります。 せいぜい15mm厚 くらいが適当でしょうか。 仕切り板部分の1枚ごとにずらしてゆく位相は上から下まで同じにする必要もないと思われるので(もしかしたらスパイラルの動作 上好ましくないかもしれませんが)重ねる面積との兼ね合いで設計すればよいと思っています。
なぜここまで拘るかというと、φ200mmくらいのスパイラルになると、幅10mm程度の平型キャプタイヤケーブルによる方法では、どのみち剛性 不足であることが上げられます。 現行の3D-subakoもその点で不利でして、音への悪影響の程度を心配しつつ聴いている状態です。 これの打開策と しても、有効です。
ただし、ディスク法は容積効率が悪いです。今より更に巨大化必至。(汗)
先日電源を更新して飛躍的に音が良くなった、うちのRasPiオーディオ。 今度は、DACの出力用キャパシタ(コンデンサ)の変更を試みました。
今回も作者の方の改造例を参考に、だけど8千円のDAC基盤のパターンカットは後戻りできないので踏み切らず、キャパシタ交換のみ実施してみました。 何しろ、このコメントで大事なヒントを沢山いただいていて、これはもうやる気満々になっちゃいますね。
キャパシタだけの変更では、音が荒れる方向に変わるだけでグレードアップ方向ではない、とのことですので、パターンカット、150Ω抵抗の追加もやってみました。(注記:150Ωは最適値ではないようです。作者の方は560Ωを使用中とのことです。私は手持ちがありませんので、しばらくは150Ωで使います)
(追記)2016/6/4 作者の方の最終稿は、更に560Ωに9.1kΩを並列接続に変更されています。現時点ではこちら。
今日は別ブログに書きましたが、荒川で小松菜マラソンハーフを走ったあと、少し足を伸ばして秋葉原の千石電商にてパーツを調達。
もともと、イーディオさんから購入した状態では、4700PFの黄色いポリエステルフィルムコンデンサは取り付けられておらず、どうぞご自由にお好みに交換ください状態。 でももうはんだ付けした後だったので、例によってはんだ吸い取り線で一旦外します。 念のため外した状態で音を出してみると、、 右側から音が出ない!
この間の抵抗値を図ってみたらL側20数kΩに対してR側は0Ω・・ がちょーん、はんだごてを長時間当てすぎたか。。?
気を取り直して、何度かはんだごてを当てているうちに復活。。 ふう、我ながら手元の不器用さにはいやになるなあ。
抵抗追加無しバージョン
多少の音の劣化は覚悟のうえで、リード線をはんだ付けして、適当に容量を想定して仮に線をよじってつなげてみた。 以下の使用数はLR両CH分です。 片側で 2 x 2200 + 470 = 合計 4870PF
| 種類 | 容量 | 単価 | 使用数 |
| ポリエステルフィルムコンデンサ | 2200PF | 10 | 4 |
| ディップマイカコンデンサ | 470PF | 300 | 2 |
高域のなんとなく薄っぺらい感じがなくなって、立ち上がりが速く、厚みの感じる音になった。 高域のしっかり高音質で録音されたディスクで聞くとよくわかります。 例えば、蟲音・続 など音像の存在感がすごくよくなりました。 中域~低域も少し変わった気がするけど、このスピーカーと部屋では限界を超えているのでわかりづらい。
電源変更だけの状態では、拙作Tornadefly+は良くてもクリアミントで聞くと中域~高域のクオリティがちょっと今一つだったのに、この変更できっちり良い音で鳴るようになりました。 不思議なもんです。
抵抗追加バージョン
その後、パターンカット+150Ω抵抗を追加したので、その際のコンデンサ容量も追記します。 片側で 2200 + 470 + 47 = 合計 2717PF
| 種類 | 容量 | 単価 | 使用数 |
| 音響用被膜抵抗 | 150Ω | 30 | 2 |
| ポリエステルフィルムコンデンサ | 2200PF | 10 | 2 |
| ディップマイカコンデンサ | 470PF | 300 | 2 |
| ディップマイカコンデンサ | 47PF | 220 | 2 |
抵抗追加・容量変更で、高域の厚みは引っ込み、その分細かい音が出るようになった。 繊細で、高域も奥側に広がる感じがする。 低域も量感が増したような気がする。
この違いは、アナログの変化ですねえ。アナログ回路のコンデンサを変えたんだから当たり前なんだけど。 けれども、単にアナログ的な変化ではないような気もするんで、作者の方のコメントにもあったように、ES9023は独特なんだなあきっと。理屈はともかく、やってみないとわからない世界ですねこれは。 そして思うに、改造順序としては電源変更を先にやって、ピントが合った状態にしてからDACをいじらないと、順序が逆ではバランスが崩れたり効果がわからなかったりしそうです。
今までの音の変化
さて、どれだけ良い音になったのか、完全にPC+X-DDC+DC-61の音を超えて上級機を飛び越えて高級機の領域に踏み込んでいる気がするので、そろそろ自分の中でプラシーボ込みでの点数をつけてみようと思います。
| 点数 | |
| 普通のノートPC + X-DDC + DC-61 | 10 |
| RasPi3+イーディオDACノーマル | 5 |
| 同、電源変更 | 9 |
| 同、キャパシタ変更 | 12 |
| 同、抵抗追加+キャパシタ容量変更 | 13+ |
こんな感じかな。 高域だけなら、15点付けても良いくらいなんだけど。  そろそろスピーカーとアンプ(Marantz PM-14SA-ver2) の音で決まっている感じになってきたので、これ以上の煮ツメはこの環境ではほぼ困難です。
そろそろスピーカーとアンプ(Marantz PM-14SA-ver2) の音で決まっている感じになってきたので、これ以上の煮ツメはこの環境ではほぼ困難です。
抵抗追加+キャパシタ容量変更では、まだキャパシタ容量の詳細の煮ツメができていません。 抵抗追加無しよりは明らかに良くなっているのですが、どの程度良くなっているのかの評価がとても難しいですし、煮ツメはも困難な状況です。リード線もよじってあるだけなので、時間とともにすぐに劣化してくるんで、音の判断も狂ってきてしまいます。
パターンカットして抵抗を追加するテストをするために、作者の方も使われている黄色基盤DACをポチりました。 6月上旬に入荷予定です。 千円程度なので、パターンカットで抵抗追加して好みの音が出なくてもダメージ少ないですからね。 
とはいえ結局、現行の緑基盤でもパターンカットしました。 テスト状態でリード線を出しているので、そこをショートすれば抵抗値的にはもとに戻ります。(笑)
新年おめでとうございます。
昨年は色んな意味で大変な年でしたが無事に年末を迎え、穏やかな年始を迎えています。
今年もよろしくお願いします。
恒例となった新年の抱負。
今年は、そろそろ慣れてきた新たな職場で「温故知新」にしようかと考えたのですが、もう少しアグレッシブに「革新」を入れて、造語
とします。
- 温故知新:前に学んだことや昔の事柄をもう一度調べたり考えたりして、新たな道理や知識を見い出し自分のものとすること。古いものをたずね求めて新しい事柄を知る
- 更に改めるものは積極的に取り組む
という意味合いですが
- 新たな職場で、これまでの自分の良さを見つめつつ、環境に適応して変わってゆくこと
- 職場の習慣や不文律などを理解し尊重しつつ、新たな息を吹き込み変えてゆくこと
を目標として新たな気持ちで頑張ります。 






















 2
2