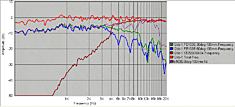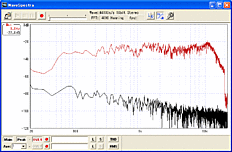日記一覧
当サイトに登録されている日記一覧



先週3連休最終日に開催された、集まれ!塩ビ管スピーカーの関東オフ2010。
そこに参加した私のスピーカー、Kids on Jenga が、(とりあえずそのまま)我が家のリビングスピーカーに復帰しました。 
実は、オフ会終了後は下部積層スパイラル部分を外して元のケーブル巻きスパイラルに戻すつもりだったのですが、このデザインが案外我が家のリビングに溶け込んでおり、家内の評価も上々だったため、そのまま居座ることになった次第。
オフ会の会場は低域過多気味なので、下部の可変積層スパイラルは少し絞リ目の設定で臨みましたが、 我が家のリビングは割と素直な特性なので、もう少し低域の量感を出したいと思います。 積層枚数を減らすか、枚数維持で位相回転角を小さめにするか、近々やってみようと。
なお、本来の積層スパイラルの実験もそのうち手がけようと思いますが、その時には低域の出易いCool Bizを使おうと思います。
- 関連リンク
- 10月11日(月・祝)のオフ会の様子
- オフ会時のKids on JengaのYouTube動画
- オフ会向けの選曲
- JENGA製作(2010-10-5)
- Kids on JENGA(2010-10-7)
Twisterの積層各板のくりぬき?spiralフィンの45度の面取りが終了しました。
画像のL側は、M8-L480mmの六角溶接ボルト(ユニクロメッキ)を仮止めしてみたところ。長さはやや長めですが、接着剤をつけて締め込めば、ちょうど良い感じになりそうな予感。
スパイラルのフィンは、この時のような風車模様にするのは「やめ」にしました。 なんといっても、加工が大変すぎますし、強度も落ちるし、どれだけ音質向上効果があるかというと ?疑問符がつきます。
よって今回は現実的なところで 一律45°程度にグラインディング加工としました。 最内周は大体滑らかに繋がってます。 まあ、これでも作業時間はほぼ3時間、かかってしまいましたが。 (汗)
現状の完成度、40%くらいですが、最大の山場を乗り切りましたし、残りの暫くは、まとまった時間が無くても進む内容です。
・ブロック毎に接着
・ツイーター取付穴加工
・一部の内部補強
・バッフル板加工・接着
・ブロック毎に内部塗装
・外部仕上げ塗装
・音だし?ネットワークおよび下部音響ダクトなど各部の微調整
という手順で進めます。 GW後半は出かけることが多いので、その後の平日、仕事がない時にでもコツコツと・・
タグ VPN ubuntu
先日も、繋がってはいたのだが、どうしても公開サーバーにアクセスできない。
思えば以前ホストOSをubuntuに決めるとき、テストしたのは
PPTP-VPNで認証されて繋がった
というところまでで、実際にアクセスしていなかったのでした。  ...
...
先日、蘇我みくすクラブのサイトを更新したばかりですが、
さんぶクラブ別館が今まであまり活用できていなかったので、そこに取り込形で、合同サイト化してみました。 今までと同じURL ( http://www.sanbuclub.com/ ) で、同じ内容が表示されます。 携帯でも同様。
これで、それぞれの予定を一括で確認でき、便利です。
もちろん、管理が楽になることも何よりメリットの一つなのですが。 
なお、デザインも少しポップな物に変えてみました。
皆さん、来てね?。
Twister、 現在 subakoをあっち向いてホイ! して実験中。
現状subakoにFE103Eスルー x 1本 (30degオフセット) + ツイーターでテストしている限り、 かなり良い音を奏でます。 音場の見通しや弦の繊細さ、躍動感、音域バランスなど、FE88ES-R1発のsubakoを軽く凌駕します。
ただ、FE103Eを内向きにすると音像・音場感が損なわれるようです。よって、ツイーターを少し内向きとし、FEは2個とも外向きに変更。
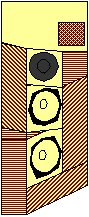
|
構想はこんな感じです。
正面を基準とすれば、
ツイーターは-15deg、
FE103E-1は+15deg、
FE103E-2は+45deg、 です。
ツイーターを基準にすると、
FE103E-1は+30deg、
FE103E-2は+60deg、 です。
ARTAで距離100mmで測定し、simuった結果は↓のようになります。 10KHz以上はツイーターの能率が少々低めですが、外向きFE103Eの高域のエネルギー増分があるので、ツイーター正面でのバランスはこのくらいが良さそうです。
また、5?10KHz付近が干渉でうねってます。
こ れは、フルレンジ側にネットワークが入っていないため、位相回転具合がツイーターと異なることから生じており、 この方法(フルレンジスルー)を採用する からには、致し方ありませぬ。 うねりの大きさが小さいので、元々のFE103E-0degよりも十分にフラットですね。
そろそろ設計製図に着手できるレベルに到達したように思います。
そして当初の見込みよりも相当に音の良いスピーカーにできそうです。 楽しみになってきましたよ?!
今日は、例のアレの話です。 アレですよ、アレ。 え・・分かりませんか?
昔の記事にも書いた、同族会社の損金不参入改悪の話ですって。 忘れたなんて言わないでくださいね?。こんな大事な話を。
12月14日に自民党税制調査会がまとめた、平成19年度税制改正大綱(pdf)で、特殊支配同族会社の基準所得金額を、昨年設定した800万円→1,600万円に引き上げる、というのが盛り込まれています。
いつもの、じぇーりっさん! のぺーじでも早速記事になってました。
不謹慎かもしれませんが、私としては一安心です。 これで数年は大丈夫ですし、そこまで利益と収入を得ても、不公平で余計な税金は納めなくて済む。
→だから頑張って仕事を前向きに出来る。
→経済に貢献できる。
→経済が活性化し、景気が上昇する(?まさか・・)
がしかし、これで能天気に喜んでいてはいけないんですよね。 だって、弊社は「たまたま1600万円には到底及ばない」ために免れているだけで、不公平で余計な追加税金を納めなければいけない零細企業はまだまだかなりあるはずですから。
大体、最初の思想が「個人事業との不公平感の解消」 などと尤もらしいことを言って800万円に設定しておきながら、じゃあ1,600万円ってどういう数字? 「えーい、わからんから倍にしとけ!」 と税制調査会の誰かがぼそっと言ったらそうなった、としか考えられまへん。 何たる、このいい加減さ! 「行き当たりばったりで、取れそうなところから取る」だけの、理念の欠いた税金政策。
そもそもこの昨年の改正そのものがおかしいのであって、基準金額を倍にしたからって、「改悪反対!」の声を弱めちゃいけません。 ダメなものはダメ。 今回の後退が「ダメさ」を物語っています。 税理士会の皆様、頑張ってくださいー。
***
20061218 追記
下記サイトを見ていると、昨年はこっそり「大改悪」しておきながら、今年はお詫びもいれずに 「ベンチャー支援」に大々的に入れているそうな。 もう常人には理解できまへん。 はい、与党に嘲笑。
久々のオーディオネタです。
下記JSP研究所の 「歪まない重低音のスピーカー」 のページを読んでみてください。
JSP研究所のページ
まだその音を聴いたことは無いのですが、低音の増強/伸延効果があるらしく、 JSP研究所のサイトと、 集まれ塩ビ管スピーカー のサイトに、自作された方の作例が報告されています。
私の好みとして「軽くて深い低音」「軽くて速くて深い低音」(061102加筆)を追い求めていまして、 だからこそ最近「3D-SPIRALホーン」にこだわってきたのですが、 ここにJSP方式という新たな興味が加わりまして、 その動作を直感的に考察しています。 今日はその内容を書き留めておきたいと思います。 読まれた方の感想をお待ちしています。
【前置き】
まず、この記事は、JSP方式の低音増強の原理(?) を私が勝手気ままに推測したものです。 全くの妄想に過ぎないかもしれませんし、完全な的外れかもしれません、ご容赦ください。
| [推測1] JSP研究所のページを見ると、その最大の特徴は ユニットの周囲に同心円状に配置された複数のバスレフポートだと考えます。 この同心円状のダクトからの空気輻射が、ユニット前面の空気と連動して共振することで、低域の増強/伸延に結びついているのかと思います。 |
| [推測2] 一般的に、バスレフポートをユニット近くに置いたからといって、低域を増強させたり延ばしたりすることは難しいと思います。 それどころか、バスレフポートの共振周波数より下では、ユニットとポートの間での空振りが早めに訪れて低域が急降下することもありそうです。 JSP方式のように同心円上にダクトを配置することで、これとは違う何らかの作用があるのかもしれません。 例えば、ユニットに対して2つのポートを直線状に対峙する位置に設ける場合を想定すると、反対側のポートの振動が、空振りの際の空気の流れを抑える方向に作用するであろうことは、容易に想像できます。 その状態はすなわち、ユニットとポート前面の空気が同期して共振している状態と考えられます。 更に90°間隔で4本のポートを配置することで、その効果は高まると思われます。 ポート前面の空気が(実際にはその空気の質量が) ポート内の空気と同期して共振すれば、その時の振動周波数は下がります。 下記バスレフポート共振周波数計算式で ポート面積Sと空気室内容積Vは変わらず、ポート長Lが大きくなったことと等しい効果です。 ★ Fd=160√(S/(V*L)) ・・[1] (実際にはLに実効ポート半径rなどが加算され ますがここでは省略) |
|
[推測3] ポート前方の空気の同期共振する質量と共振周波数の伸びの関係を、上記計算式 [1] から計算してみます。 まず、[1] 式から定数およびポート面積Sを一定として下記 [2] 式を考えます。 ★ 1/√(V0*L0) ・・[2] ここで、 仮に JSP方式でポート前方の同期共振空気質量が、ポート内空気質量の3倍と仮定して考えるとすると、[2] 式は |
| [推測4] 次に、 空気室内容積とダクト長を変えて、ポート共振周波数を同一にした場合に、 [2] 式の状態はどうなるかを考えます。
まず 、空気室内容積を2倍にして、同じ共振周波数を得ようとすると、ダクト長は1/2で良いことになります。 続いて この[4] 式でJSP方式で [推測3]と同じ質量が同期共振するとすれば、
★ 1/√((2V0)*(3L0+L0/2)) =1/√(7(V0*L0)) この結果、同じポート共振周波数ならば 空気室内容積が大きいほど、 JSP方式による低域伸延効果が高まるということになると考えられます。 |
【まとめ】
あくまで推測の積み重ねで考察してきましたが、直感的にこのような効果はありそうに思っています。 どうでしょうか。
☆☆ ここまで考えると、作ってみたくなりますねえ。
**061101 追記
この推測は、バッフル前面の空気がダクトと同期共振する、という考え方なんですが、 どうも 「バッフル形状が正方形や円形でないと効果が出ない」 ということが引っかかりまして、 もしかしたら 「空気室内の空気の一部が、同期共振しているんではないか?」 などと考え始めています。 空気室内の空気が分割振動してるんかいな。。
タグ PC ESXi ハード
友人の、はるちゃん@スマイルから依頼を受けてPC部品を購入、本日一通り入荷した。

組み立ては、はるちゃんの自宅で行う約束なので、その前に部品を少々拝借していくつかの実験中。(もちろんご本人の了解の元ですよー。) 
...
タグ VMwareServer qpopper
私がVine Linuxを使う理由は、日本語環境だけではありません。 サーバー用途にしても、押さえるところは「使いやすく」準備されていることです。
qpopperのrpmバイナリパッケージのバージョンは、(VineLinux3.2の頃から既にそうだったのかもしれませんが) qpopper-4.0.9-0vl3 となっています。
デフォルトバイナリーでは「Pop-over-SSL使用可」 「APOP使用可」 になっていますが、「Pop?beforeSMTP」つまり「DRAC」は使わない設定です。
しかし、ソースrpmをダウンロードしてspecファイルを見て気づいたのですが、rpmリビルドにてspecファイルを1文字書き変えるだけでコンパイルオプションが「DRAC使用」に変更できるようになってます。 こうして自前rpmをちょちょいと作っておけば、他のサーバーにもそのまま展開可能です。 Vine Linux、細かい気配りありがとうございます。
そんなわけで、以下はVine Linux4.0[10/29現在RC1]で 「Postfix+qpopper」+「Pop-befereSMTP」+「Pop-over-SSL」を構築する手順の備忘録です。
...3Dスパイラルホーンスピーカーの可能性を追求するブログ・・
なんて大上段に構えるつもりではなくて、少しでも自分の満足を満たす音にしたい。 そのためには、研究も必要ですね。
音の実験室:自作バックロードホーン・スピーカー 創始者:Takenakaさんのサイト
☆Helix H75 の製作?視聴 :Akkieさんのサイト
自作3Dスパイラルスピーカー製作記 :くまさんのサイト
★ 私のHP内の、 自作スピーカーのページ ★
★ 私のHP内の、 Takenakaさん宅訪問記(F特掲載) ★
新作は名づけて「3D-ELBOW-R」。
VP150塩ビ管を斜め45°カットし、エルボ状に接着。
スパイラルは2重らせんで、「ひらべった型」です。
ユニットはFostexのFE88ES-Rを使っていますが、高音の伸びに比べて低音の伸びがイマイチなので、F特を測定しつつ、いろいろいじっています。 何とか聞けるレベルになったかな。
50?100Hzはバスレフ的、100?200Hzは音圧は低いけどバックロード的な音がします。
(F特は、2mステレオ中心、サインスイープです。)
音場感と音像のコンパクトさは、さすがですね。
でも、塩ビの筒がピアノの中音で振動が多くて・・
空気室を、塩ビ管 -> 球形積層集成材に作り変えたくなってきた。
資料: FE88ES-R(PDFファイル:FOSTEXのサイト)




 3
3